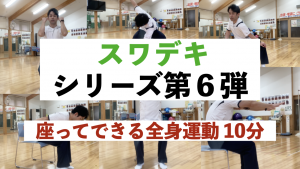こんにちは。上伊那生協病院の回復期リハビリテーション課で主任をやっています、作業療法士(以下、OT)の小林です。
早いもので2022年も、残り1か月。今年もなんだかんだコロナの影響で、当院のリハスタッフも行動制限がある中で日々の臨床に悩みながら奮闘する毎日を送っています。
そこで、今回は、リハブログのテイストをちょっとだけ変えて、新人OTの波多野さん(信州大学卒)に対談方式で、いろいろインタビューをしてみたいと思いまーす。

小林:4月に入職して、はや半年が過ぎましたが…仕事には、だいぶ慣れましたか(笑)?率直な感想として、大変だなって思うところはありますか?
波多野:学生時代と違って、生活リズムをしっかりしなきゃいけないので、最初はそれが疲れました。朝も早く起きなきゃで、夜も次の日に備えて早く寝るって感じでした。
今はそれが慣れてきて、疲れなくなりました。健康な生活が送れるようになりました(笑)。
小林:正直でいいと思います(笑)。普段の仕事はどんなことを行っていますか?
波多野:回復期リハ病棟なので、毎日、リハビリに入って、身体機能の介入中心に患者さんに関わっています。あとは、看護師さんや相談員の方などとコミュニケーションをとることを意識していて、OTなので、患者さんの生活の様子を確認しながら、退院に向けて準備・支援を行っています。
あとは、OTの中で、運転チームに所属していて、OTっぽくて楽しくなってきています。そもそも評価内容や訓練についてなにも知らなかったんですけど、やっと内容や流れがわかってきたので、分析できるようになりたいです。
小林:OTっぽいって話が出たけど、OTっぽいってなんだろうね。例えば、運転と一言で言っても、いろいろな捉え方ができるよね。仕事や畑に行くための移動手段として捉える人もいれば、ドライブすることで気分転換を図ったりできるなど、その人にとって捉え方も変わって、まさに“作業”って感じで捉えることができるよね。
波多野:そうですね。運転って、IADLですもんね。そう言われると、今、担当している運転リハで関わっている患者さんがいるんですが、元々、運転好きな方で、できなくなってしまって、免許を取り上げられてしまうと、QOLが下がってしまうなって思いました。
小林:病気があるから、やみくもに運転はダメ!ではなくて、障害を負った方々が、自分の病気のことを理解して、ちゃんと向き合えるように運転支援はしていきたいね。そのためにも、運転に関わるOTは評価結果から障害像の分析を行って、Drとディスカッションをできることが大事にしたいよね。

小林:あと、上伊那生協病院の新人教育は、業務時間内に、臨床に出たときに活かせる知識も含め、姿勢や動作分析のような学習的な要素を取り入れた内容を、職種関係なく、新人教育に組み込んでいるけど、どうですか?
波多野:新人教育は、業務時間内に保障されているところもあり、教わった内容が、臨床に活かせていると思います。身体のことは難しいと思ったけど、事例を通しての評価の視点なども解説されているなど、それがわかりやすかったです。
あと、指導者の方が年齢の近めな方なので、相談しやすいです。リハの雰囲気も、職種関係なく、混じって仕事をしているスタッフルームなので、先輩にも話しかけやすいと思います。

小林:上伊那生協病院のリハビリはどんな特徴があると思いますか?
波多野: 教育とかで、職種関係なく、身体機能のことを深める内容だったので、臨床の視点で、まず身体機能を見ようとする視点は強いなって思います。
自分も意識はしてますが、最近は、それだけじゃ足りないと思っています。動作の原因を考えると、身体だけじゃなくて、高次脳や本人の生活歴の影響も感じるときがあります。最近はOTなので、生活もみるけど、表情変化などをみて、いかに笑顔を引き出せるかを大事にしてます。それは、新人でもできることかなって思っています。
小林:評価から、個別性を引き出せる介入って大事なことだと思うよ。
そんな波多野さんが、これからチャレンジしてみたいこと、どんなOTを目指したいですか?
波多野:どんなOTになりたいかと言われると、患者さんのできないことに目が行きがちになっちゃうんですけど、身体のことも含め、その患者さんの大事にしていることや患者さんの潜在的なものをもっと引き出せるOTになりたいと思います。
そのために、患者さんをいろんな視点で関われるように、いろんな勉強や研修会に参加したいと思います。
小林:これって決めない方がいいかもね。今は、いろいろな可能性を考えて、自分が何に興味をもっているか、少しずつ整理できるといいなって思うよ。それで、学んだ知識をみんなで共有して、生協病院のOTを一緒に盛り上げていきましょう。今日はありがとうございましたー。
当院のOTは、若手スタッフも多く、コロナ禍もありOTをどう盛り上げていくか、主任として悩みながら日々の臨床に明け暮れる毎日です。そんな中、波多野さんのように、OTの奥深さに触れて、これからいろんなことにチャレンジしようと思っている若手スタッフと一緒に働ける今の職場環境は、自分にとって励みになっているなーと感じた瞬間でした。
生協病院では、まだまだ、来年度、一緒に働いてくれるOTを募集しております。詳細に関しては、下記のリンク先より確認できますので、ご興味がある方はのぞいてみてください。
長文にお付き合いしていただき、ありがとうございました。
上伊那生協病院 回復期リハビリテーション課
主任 OT小林 和宏
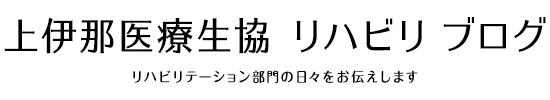




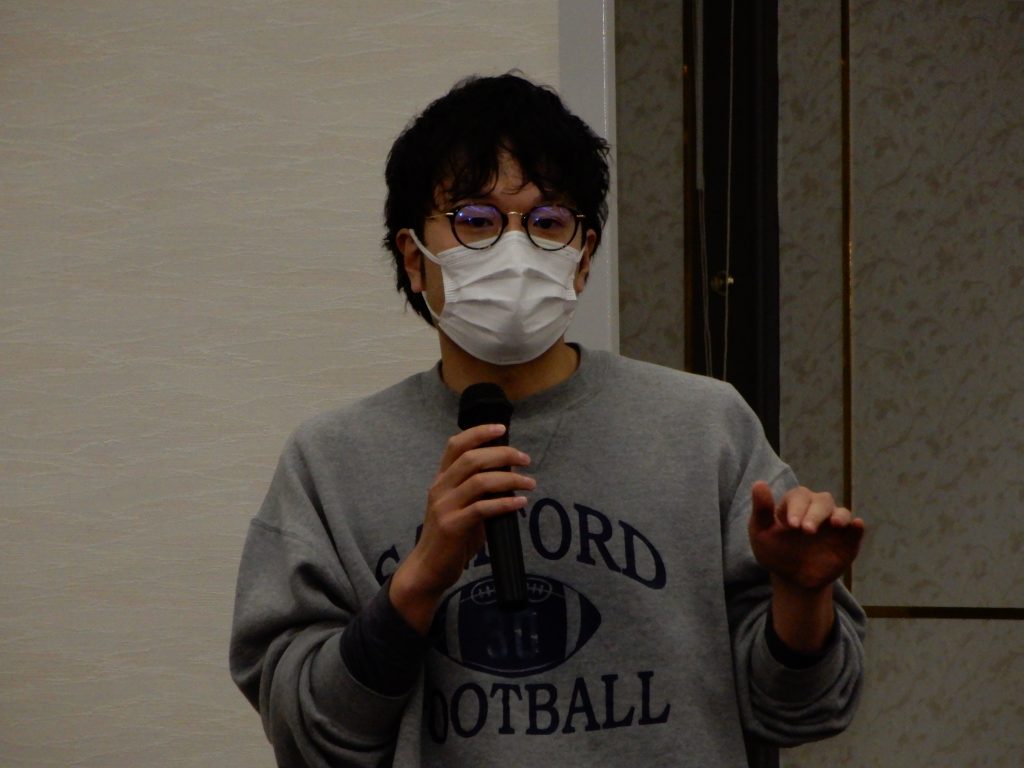
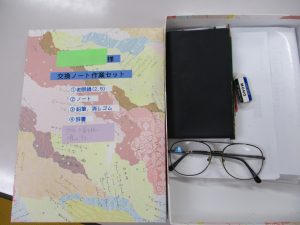
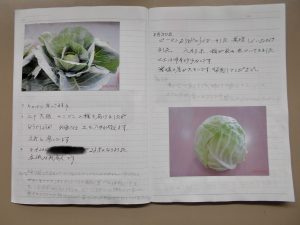






-225x300.jpg)